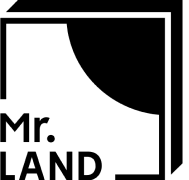【経済の動き】米国の景気後退は、いよいよ目の前に迫っているのか?
ムーディーズによる米国債格付け引き下げ以降、株価は低迷し続けていました。
しかし米国とEUの関税交が難航するなか、5月22日にトランプ大統領主導の財政改革法案
「One Big Beautiful Bill Act」が下院を通過したことがきっかけとなり、市場は上昇に転じました。
また、6月1日から発動予定だったEUへの50%関税が7月9日まで延期されると発表されたことで、株価はさらに上昇しています。
この財政改革法案には、残業代やチップの非課税化と言った景気刺激策も盛り込まれており、
これにより国民の手取り収入が増加し、インフレを相殺できる可能性があるとの見方が市場に安心感を与えたと考えられます。
現在、市場は以前ほど関税発動に対する懸念を強く抱いていないように見受けられます。
しかし、法案の完全な発効には上院の承認が必要であり、減税による財政拡大と赤字増加への懸念は依然として残っています。
それでも現時点では米国の財政赤字が国民の生活に直接的な影響うぃ与えている様子は見られません。
今後のインフレ懸念を示唆する兆候
いくつかの経済ニュースからは、関税の影響によるインフレ懸念伺えます。
例えば、大手ディスカウントストア「ターゲット」の売上高が大幅に減少しているほか、
「ウォールマート」が関税による仕入れコストの上昇分を消費者に価格転嫁しているという報道もあります。
また、JPモルガンのCEOであるジェイミー・ダイモン氏は、米経済がスタッグフレーション
(景気停滞と物価上昇が同時進行する状態)に陥る可能性は排除できないと、
以前から警告の金を鳴らしている人物の一人です。
ニュースにされることは少ないものの、企業向け融資の審査基準が厳しくなっているという事実を踏まえ、
ダイモン氏は他のエコノミストよりも悲観的な見方をしているのかもしれません。
加えて、M&A(企業の合弁・買収)も停滞しており、経済の減速傾向が見て取れます。
住宅ローン市場にも変化の兆し
企業向けは厳しくなっていますが、一般消費者向けの住宅ローンの審査基準は、現在のところ大きくは厳しくなっていません。
ただし、確実に変化は起きています。
最近では、「審査基準が比較的緩やかだが、金利は高め」というローンプログラムが数多く出てきています。
これは何を意味するのか?
実は、2008年のリーマンショック前夜にも同様の傾向が見られました。
当時と同様に、住宅ローン取扱件数の減少により利益が圧迫されている金融機関が、
2年前ほどから高リスク商品を市場に出し始めているのです。
これは需要の掘り起こしを狙った動きと考えられます。
こうした動向は、企業の業績悪化、雇用の調整、倒産増加、
そして最終邸には景気後退の可能性を示唆していると考えられます。
米国税制改革法案の注目ポイント
今回可決された米国の新たな税制改革法案には、不動産・住宅業界に関わる重要な項目が多数盛り込まれています。以下に主要なポイントをご紹介します。
- 低所得者向け住宅税額控除の強化:低所得者への税制優遇強化
住宅確保が困難な低所得者層に対する税制優遇措置が拡充され、住宅取得・維持を支援する制度がさらに強化されました。
これにより、賃貸需要や住宅市場の底堅い支えとなる可能性があります。
- 住宅ローン利子控除:ローン利子を現行水準で維持恒久化
これまで議論の的となっていた住宅ローン利子控除については、現行水準での維持が恒久化されました。
住宅購入者にとって安定した税優遇が続くことは、大きな安心材料です。
非課税枠がこれまでより大幅に拡大し、1,500万ドル(約2億1,750万円)まで引き上げられました。
これは、資産継承を見据えた不動産活用において、節税面での大きなメリットとなります。
- 機会ゾーンの優遇措置の更新:低所得地域への投資に対する税制優遇措置
低所得地域への投資を促す「機会ゾーン」への税制優遇が引き続き適用され、
地方の開発促進と不動産投資機会の創出が期待されます。
- 税制優遇のある子供向け投資講座の創設:子供税額控除額の引き上げ恒久化
子育て世帯に対する支援策として、子供1人あたり最大2,500ドルの税額控除が恒久化されました。
これにより、将来的な家計の安定や住宅購入への備えとしても活用できる制度となっています。
米国企業の仕入れ、国内回帰は本当に成功するか?
アリアンツ・トレード・グローバル・サーベイの最新調査によると、
米国企業の90%が、関税政策を受けてサプライチェーンの見直しを検討していると回答しています。
特に一部または全部を国内に戻す、いわゆる“リショアリング“の動きです。
とはいえ、実行となると簡単ではありません。
現場レベルでは「サプライヤーの選定」「コスト」「人材確保」など、現実的なハードルがいくつもあるからです。
現状、企業の多くは「複雑化しや海外の調達体制」を整理し、シンプルな国内供給網に戻したいと意向を持っています。
実際、「関税コストを価格に転嫁せざるを得ない」と考えている企業は全体の54%。
一方で「企業が吸収すべき」とするトランプ大統領の方針に賛同し、実際に自社で吸収する姿勢を見せているのは15%程度にとどまります。
企業のコスト増対策として考えられる選択肢
このような動きは各社で進みつつあります。
ちなみに、今年4月の米国の関税収入は過去最高の163億ドル。1年前の2倍以上になっています。
今後、輸入品価格の上昇で輸入量が減少することはある程度避けられないでしょうが、
政府としては10年間に1.7兆ドルの税収を見込んでいるとの試算も出ています。
国内調達だけでやっていける企業が増えてくれば?
もしこのリショアリングがある程度成功すれば、米国内に新たなビジネスモデルが定着し、
より持続性のある経済基盤が築かれる可能性もあります。
もちろん道のりは平たんではありませんが、これは米国経済が改善体質を目指す上で重要な試金石にもなると言えるでしょう。
【不動産・住宅ローン金利動向】 なぜ、いま「売り物件」が増えているのか?
株式や債券市場では、短期の取引によって価格が日々変動しますが、不動産市場は、本質的に長期投資の世界です。
だからこそ、不動産の動きには将来の経済の方向性が現れることがあるとも言えます。
いま、その不動産市場で目立ち始めているのが「売り物件の増加」です。
新規の売却物件が多く出てきている一方で、売れ行きは鈍く、売れ残り物件が積みあがって市場在庫が急増しています。
その結果、売買価格が少しずつ下がり始めているのです。
なぜいま「売り」に出す人が増えているのか?
背景には、いくつかの要因があると思われます。
まずは、経済的な理由から自宅を売却して賃貸に移る動きが増えている可能性があります。
金利上昇や生活コストの上昇で、月々の支払いが重くなってきていることも一因でしょう。
また、投資用物件を持つ人たちは「早めに売らないと利益が減ってしまう」と
判断しているケースもあります。
価格のピーク感を感じている売主も少なくないということですね。
売る判断は、どこから来るのか?
多くの売主たちは、判断材料として以下のような情報源を頼りにしているようです。
- Realtor.com、Zillow.com、Redfin.comなどの不動産関連サイトのニュース
その中でも、一番信頼感のある情報はどこからのものでしょうか?
実際の取引を基にした生の情報(不動産屋さんや投資家仲間の間の情報交換)は、最も信頼感が高いと思います。
ただし、その情報は地域限定であるため、全国的なトレンドとは異なる可能性がある点には注意が必要です。
「売りたい人が多いが、売れにくい」市場の実態
全般的には今、多くの人たちが家を売りたがっているのに、すぐには売れない状況が広がってきています。
売り物件数が増加、値引きをしてでも売りたい売主が増加となれば、必然的に売買価格は下がる方向に動きます。
こうした状況を一変させる可能性があるのは「金利」です。
金利が持続的に下がり始めれば、買い手の心理も変わり、市場の雰囲気も徐々に回復していく可能性があります。
現場でも感じる“売りモード”
今年に入ってから、私の携帯にも日に何度も「家を売りませんか?」という
不動産エージェントからの電話がかかってくるようになりました。
このような積極的な“売り込み”が増えているということは、不動産業界全体が今「売りモード」に入ってきたのは確実です。
現時点では物件価格の大きな崩壊を予想する人は多くないですが、
業界内では年末までに1%程度の価格下落が予想されています。
私個人としては、地域によってはそれ以上の下落もあり得ると予想しています。
その理由は、単に売り物件在庫の増加のみならず、景気後退が現実味を帯びてきている予想しているからです。
住宅ローン金利はどうなる?
今年の年末にかけて金利が下がってくるのではないか――そんな見方が少しずつ広がってきています。
その背景には、トランプ関税、ウクライナ戦争、イスラエル・イラン情勢、米国財政赤字、景気後退懸念など、
複数の不確実要因があます。
中でも金利が下がり始めるきっかけとして最も有力なのは「景気後退」でしょう。
実施、関税が発動されても、インフレの再燃よりも、むしろ企業業績の悪化や消費意欲の減退、
それに伴う雇用統計の伸び悩み、GDPの鈍化といった兆候が出てきたとき、
マーケットは次の一手として「利下げ」を織り込み始めるでしょう。
この夏、米国はバケーションシーズンに入ります。
学生のアルバイトも増え、雇用統計は一時的に押し上げられるかもうしれません。
また、富裕層を中心に旅行や高額消費が見られ、表面的には消費が好調に推移してくる可能性が上がります。
しかしそれでも、肝心の統計データ(特に企業決算や実質所得、購買指数など)が振るわなければ、
市場センチメントは一気に冷え込む可能性があります。
6月~7月がひとつの山と考えて見ています。
今後不動産市場をけん引するのはどこ?
これまで述べてきたように、市場に出回る売り物件の供給が増加し、売れ行きは鈍化傾向。
在庫が積みあがる中で価格も下落に向かうというのが全米の一般的な流れです。
ただし、南部や中西部については様子が異なります。
このエリアは、もともと不動産価格が比較的に安く、生活コストも抑えられていることから、人口流入が継続。
不動産需要も旺盛で、新築物件の建設も活発です。
さらに、米国の他州から企業の工場移転や新規進出などによる雇用創出も後押ししています。
その一例として、2025年5月22日にはメルセデス・ベンツが
北米本社をジョージア州Sandy Springsに移すことを発表しました。
また、現代自動車は同州サバンナ近郊にEV工場を本格稼働させています。
このように、生活コストの安さ・治安や雇用の安定・自然災害の少なさなどを背景に、
人口の流れが大都市圏からシフトしているのです。
U.S.News &World Report の「15Best Places To Live ㏌ The US(住みやすい都市ランキング)」でも、
上位15都市の内14が南部・中西部に集中しています。
- Johns Creek, GA
- Carmel, IN
- Pearland, TX
- Fishers, IN
- Cary, NC
- League City, TX
- Apex, NC
- Leander, TX
- Rochester Hills, MI
- Tory, MI
- Sammamish, WA
- Broken Arrow, OK
- Ellicott City, MD
- Flower Mound, TX
- Pflugerville, TX
(出典:U.S.News &World Report)
これらの都市は、住宅コストと生活環境のバランスが良く、今後も不動産市場の牽引役になると予想されます。
【国際ニュース】Z世代が考える景気後退のサインとは?
米国では、1996年から2012年に生まれた若者たちを「Z世代」と呼び、彼らは従来の経済指標と異なる
“独自の文化的センス”を持ち、景気の行方を図っているようです。
昔から「スカート丈が長くなると不況のサイン」と言われるように、生活の些細な変化から経済の先行きを察知する
という考え方は一定の説得力を持っています。
Z世代の考える“景気後退の兆し”も、とてもユニークにキャッチしているようです。
彼らが最初に気づいたのは、卵の価格上昇、段ボール箱の需要減少、ダンスフロアの閉鎖ぶりでした。
今ではさらに進化し、ローライズ・ジーンズの再流行、ゲリラ・パフォーマンスの増加、レディー・ガガの再登場と
いったカルチャー面の変化に注目しています。
TikTok世代が話題にしているのは「セリフ体のフォントが流行ると不況が来る」「付け爪の人気復活は節約志向の表れ」
「乱れたお団子ヘアは“投げやり感”の象徴」などという分析まで出てきました。
もっと現実的なところでは、料理宅配大手DoorDash(ドアダッシュ)と決済大手Klarna(クラーナ)の提携によって、
宅配費用を「分割払い」できるようになったという話題も。
Z世代の多くは、政府の発表する雇用統計やインフレ率などの政府公式データよりも、
生活感覚の変化のほうが現実を正しく反映していると冷静に見ているようです。
ベビーブーマーよりも将来にあまり明るい未来を見ていない世代ならではの、
自己防衛本能がそうさせるのかもしれません。
このように一見経済とあまり関係のない、些細な変化を真剣に捉えてきた人々は、過去にもたくさん存在ました。
例えば、元FRB議長のアラン・グリーンスパン氏は「男性用下着の売上動向」を密かに注視していたことで
よく知られています。
誰にも見られないところにかける支出が減るというのは、不況下の人々の行動として理にかなっているわけです。
また、景気の悪化から家計に余裕がなくなると、女性が“手頃な贅沢品”として口紅を買う傾向があるとされ、
これは「リップスティック・インデックス」と呼ばれています。
高額品は買えなくても、ちょっとした自分へのご褒美を求める心理がそこにあるのでしょう。
ヨーロッパ諸国にも見られる“口紅現象”?
このZ世代の視点を見ていると、ふと頭に浮かんでくるのが、今のヨーロッパ諸国です。
特に英国・フランス・ドイツです。この3カ国は、捨てに勝敗の方向性が見えているウクライナ戦争に対し、
今もなお巨額の支援を続けています。
これはまるで女性の口紅現象ではないか?と感じてしまいます。
ドイツは再軍備へと舵を切り、フランスや英国もそれぞれ国内に多くの問題(自国の景気悪化、国内の混乱など)を
抱えたまま、国としてのアイデンティティーを模索しています。世界中が不安を感じているのでしょう。
“自分たちの生活が苦しくなったとき、つい手が伸びてしまうささやかな贅沢”――それが国家レベルでも
起きているとすれば、これは世界が不安に包まれている一つの証かもしれません。
今後世界中の男性たちが新しく下着を買えるようになり、女性たちが口紅を買いすぎないで済む日が来ることを、
心から願いたいものです。
【豆知識】
過去4週間で不動産中間価格の下落が大きかった都市ベスト5
価格が下がり始めたとはいえ、どこが特に早く下がっているのか?
そんな素朴な疑問に答えてくれる最新データがあります。
過去4週間で中間価格の下落率が大きかった都市ランキングは以下の通りです:
- Oakland, CA (-5%)
- Dallas (-3.4%)
- Austin, Texas (-3.1%)
- Tampa, FL (-2.4%)
- Houston (-1.2%)
(出典:Marianne Garvey U.S. Real Estate Reporter)
※彼女はRealtor.comの契約ライターとして、米不動産市場の動向を独自にレポートしています。