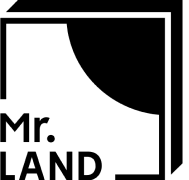【経済の動き】統計の危うさ
6月3日発表された5月の米製造業景況感(ISM製造業総合景況指数)は48.5と、3カ月連続の縮小、かつ市場予想を下回る結果となりました。水準としてもリーマン・ショック後の2009年以来の低さでした。これまでは製造業の景況指数が下落しても、非製造業の堅調さが米国経済全体を下支えしてきましたが、6月4日に発表された非製造業総合指数もついに50ポイントを割り込みました。
製造業に続き非製造業までが収縮傾向を示すのは、典型的な景気後退へのシグナルです。
しかしそうした兆候にもかかわらず、主要メディアや一部のエコノミストは「米国経済は底堅い」との見解を繰り返しています。
同時に、労働市場に関するデータも不安定な動きを見せています。雇用動態調査(JOLTS=Job Opening and Labor Turnover Survey)では、求人件数が19万1,000件増加したものの、解雇件数も増加しています。米国内の経済見通しが悪化する中でこの動きは、雇用市場の減速と一致する流れです。さらに、米ADPによる民間雇用者数の発表(6月4日)では、2年ぶりの低い伸びとなり予想を大幅に下回りました。この指標データは、実際の給料明細発行の情報に基づき雇用者数を把握しており、速報性と実態の近さという点で注目すべき指標です。
こうしたISMデータ、求人データ、さらにADP雇用データの複数の指標が軒並み弱含む中、市場では「いよいよFRBが9月から利下げに踏み切るのでは」との観測が強まりつつありました。ところが、米国労働省が発表した6月の雇用統計では。13万9,000人の雇用増と、予想を上回る結果が示さされました。雇用の伸びは減速した一方、賃金の上昇幅は予想以上。これを受けて、再びFRBによる9月の利下げ見送りの見方が浮上し、米国債利回りが上昇。これに連動して住宅ローン金利も上昇しました。ドルも買われ、6月9日(月)には円が144円台半ばまで下落する円安が進みました。
ただし、ここで無視できないのが「統計値の修正リスク」デス。米国の雇用統計など主要経済指標は、ほぼ例外なく1-2か月後にデータ修正が入ります。多くの場合、雇用者数は下方修正される傾向にありますが、初回データのインパクトがあまりに強いため、市場は速報値ばかりに反応し、より精度の高い修正データにはほとんど市場が反応せず、そのことに驚かされます。
つまり、市場は「より正確な事実」ではなく「速報として出された数字」に過剰に反応しやすい構造にあるということです。
仮にある日突然、「申し訳ない、実は経済の実態はもっと悪かった」と公式に修正されたとすれば、そのタイミングで株価が急落し、国債価格が上昇(=金利低下)するという展開も十分にあり得ます。
統計の速報値が市場の判断を大きく左右している現状では、事後的な修正がもたらす影響が軽視されがちですが、実務に携わる立場からすれば、そうした「後出しの真実」が市場を大きく揺るがすリスクに常に目を配る必要があると考えています。
二つのインフレと政策的示唆
インフレには大きく分けて二つのタイプがあります。一つはディマンドプル・インフレ(需要拡大型)、もう一つがコストプッシュ・インフレ(供給コスト型)です。一般的に、景気拡大と共に人々の購買意欲が高まり、需要(ディマンド)が供給を上回ることで物価が上昇します。このように、需要サイドに起因する物価上昇をディマンドプル・インフレと言います。価格が高くても欲しい商品が売れる状況では、企業は収益を拡大でき、設備投資や雇用拡大が促されます。結果的に従業員の賃金も上昇し、再び消費が活発化するという「良性の循環」が生まれます。日本の高度経済成長期、特に1970年前後が典型例です。短期貸出金は6.25%と高水準でしたが、それ以上に所得が上昇したため、インフレが生活を圧迫したことは限定的でした。
一方、原材料価格の上昇や人で不足など、供給サイドのコスト増加が原因で起こるのが、コストプッシュ・インフレです。この場合企業はコスト上昇分を価格に転嫁せざるを得ませんが、コストの急激な上昇により消費が冷え込み、企業利益の圧迫や景気後退のリスクが高まる懸念があります。
ディマンドプル・インフレ(需要起因型)の対策は比較的明快です。生産設備への投資などにより供給力を高めることが求められます。旺盛な需要を背景に、景気全体は拡大基調にありますので、共有の強化はそのまま経済の好循環を後押しします。
コストプッシュ・インフレ(供給コスト起因型)においては、むしろ需要喚起策は重要です。なぜなら、物価上昇が家計を圧迫し、購買意欲が低下しているためです。こうした局面では、現在が最も即効性のある対策として有効です
では、現在の米国(そして日本も同様に)はどちらのインフレでしょうか。多くの指標や状況を見る限り、コストプッシュ型と見るのが妥当です。エネルギー価格の高騰や物流費の上昇、人手不足による人件費の上昇など、供給コストの圧迫が強く働いています。この状況下では、可処分所得を増やすことが鍵です。手段としては、減税、利下げ、業界・消費者への支援金給付などが考えられます。また、日米ともに輸入依存度が高いため、中長期的には国内生産を増やすことで、将来のコストプッシュ・インフレを予防する視点も重要です。
このように見ていくと、現在トランプ大統領が進めている減税政策や、製造業の国内回帰の促進は、将来を見据えたきわめて現実的な政策であると言えるでしょう。現在、米上院で審議中の予算法案が成立すれば、企業、個人の双方にとって可処分所得が増え、それがインフレ抑制につながる効果が期待されます。
また個人消費が活発になれば、税収も増加し、財政赤字の改善にもつながります。ただし、こうした効果が表れるには一定のタイムラグがある点に注意が必要です。米国では全員が確定申告を行うため、勤労者はまず源泉徴収され、確定申告申請後に還付金を受け取るシステムです。そのため、還付金は一時的ながらもボーナスのような効果をもたらし、消費を後押しする役割を果たします。もちろん税額が引き下げられれば毎月の手取りも少しは増加しますが、やはりまとまった金額が手元に入ると、消費者の財布のひもが緩みます。
こうした事情を踏まえると、現在トランプ政権が進めているインフレ対策・景気対策は、短期的な可処分所得の拡大と、将来の供給力強化の両面に働きかける施策として、非常に理にかなっていると言えるでしょう。海外からの投資増加の動きもみられる中で、経済の先行きには明るさが感じられる状況と考えています。
ドルは下落し続けるのか?
近年、「BRICSの台頭とドルの覇権が衰退し、ドル離れが進むのではないか」「国際決済におけるドル需要の減少が、ドルの下落を招くのではないか」と言われてきました。しかしながら、現状を冷静に分析すると、その心配はあまりなく、ドルが基軸通貨としての地位を失う可能性は極めて低いと考えています。
まず第一に、地政学的要因としてのBRICSの分断があります。トランプ政権下の外交政策によって、ロシア・インドとの関係強化が進められ、中国に対しては経済制裁の強化が続いています。その結果、BRICS諸国の結束には綻びが生じており、「反ドル圏」の形成が構造的に困難になりつつあるのが現実です。
第二に注目すべきは、理由は先月の中東歴訪による戦略的成果です。米国はOPEC諸国、さらにはロシアとも一定の連携を図りつつ、原油の安定供給と価格維持に関する合意形成を主導しました。これにより、原油取引におけるドル建て決済(いわゆる「ペトロダラー」体制)の再強化が実質的に図られた形です。
マスメディアでは「中東との大型投資案件」を強調して報道していましたが、実際のところ、それ以上に重要なのは、原油決済通貨としてのドルの地位を改めて確認・強化した点です。これは長期的なドル需要を支えりものであり、ドルの下落懸念を大きく後退させる要因と言えます。
以上を踏まえると、少なくとも現時点においては、ドルが大きく下落し、国際決済通貨あるいは基軸通貨としての地位を喪失するような事態は、現実的ではありません。むしろ、外交・通商両面での戦略が奏功すれば、「強いドル」のもとでの安定的な経済成長という道筋も十分に描ける状況です。
【不動産・住宅ローン金利動向】 Fannie Mae(連邦住宅抵当公庫)の予想
Fannie Maeは6月3日、住宅ローンに関する予測を公表しました。
その内容の中で、住宅ローン金利は2026年末までに6%を下回る水準まで低下するとの見方を示しています。この予測の背景には、インフレ率の安定と、FRBによる政策金利の引き下げ開始が視野に入っているという前提があります。特に9月ごろまでには関税問題をめぐる不透明感が払拭され、経済環境が落ち着くと想定されています。またFannie Maeの予想では、GDPの緩やかな上昇傾向や不動産売り物件の増加といった要素も、楽観的な見通しを支える材料としています。
とはいえ、現時点では住宅ローン金利の高止まりが突いており、売買市場は依然として低調。今後さらに不動産不況が深まる可能性も指摘されています。
(出典:Economic and Housing Outlook5月版より)
不動産不況は買主には有利
不動産業界には「不動産は不況の時に買うべし」という格言があります。不況時の購入には以下の5つの利点があるからです。
- 不況になれば金利が下がる傾向にある
- 売り物件が増え、選択肢が広がる
- 売主との価格交渉が有利に進みやすい
- 市場の過熱感がなく、冷静に検討できる
- 景気回復に伴って資産価値の上昇が期待できる
住宅ローンの申請件数は対前年比では増加しているものの、直近の前期比では減少に転じています。この傾向は売り物件数(Inventory)の増加と、住宅ローン金利の高止まりが影響していると考えられます。
しかしホーム・エクイティ・ローン(住宅担保ローン)の減少率はごくわずかにとどまっています。この事実は、生活費の捻出や、高金利のクレジットカード債務の返済、あるいは車のローン支払いといった目的で、庶民が持ち家の資産価値を活用しながら毎月の出費を何とか抑えようとしている現状を浮き彫りにしています。
このような状況下で、新たに関税が発動され物価がさらに上昇すれば、家計を直撃し、消費活動が一段と冷え込むことは避けられないでしょう。結果として、景気は後退局面に向かう可能性が高まっています。
実際に、人口100万人以上の都市を対象した不動産購入ローン申請件数の対前期比較減率を見ると、以下の5つの都市で著しい現象が確認されています。
- Austin, Texas (-38.5%)
- St. Louis (-37.8%)
- Rochester, NY (-36.6%)
- Houston, Texas (-35.7%)
- Indianapolis (-33.5%)
(出典:ATTOM https://www.attomdata.com/)
この数字は、単なる金利や物件数の問題にとどまらず、家計の切迫と経済的な不安感の広がりを物語っていると言えるでしょう。今後、政策対応の遅れが続けば、不動産市場のみならず、消費・雇用・金融を含めた幅広い領域での影響が顕在化するリスクもあります。
【国際ニュース】ロサンゼルスで不法移民の強制捜査に対する抗議デモが激化
6月6日夜、米国のICE(移民・税関捜査局)が入国管理法違反の疑いで44人を逮捕したことを受け、ロサンゼルスダウンタウン周辺で抗議活動が激化しました。
もともと移民人口が多く、その中には不法移民者が多く居住する地域で、地域住民を含むでも参加者の一部がICE職員に対して暴行を振るい、車両のタイヤを切り裂き、公共インフラを破壊するといった行動に出ました。
左派の急進活動家グループ「アンティファ」が抗議活動を煽動し、事態は一気に暴徒化、お決まり略奪行為も発生。一部地域はまるで内乱状態のような混乱に陥りました。
ロサンゼルス市のカレン・バス市長と、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は、強硬な制圧措置を取らず、混乱を抑えきれない状況が続いたため、トランプ大統領は連邦政府の権限に基づき、州兵の派遣を命じました。
通常、州兵は州知事の指揮下にありますが、法執行当局が治安を維持できない場合は、大統領が州兵や兵士の動員をする権限を持っています。
今回はペイト・ヘグセス国防長官の指示により、700人の海兵隊が支援任務として投入されました。
これに対してニューサム知事は「州兵の派遣は違法」として州兵の即時撤退を要求しています。
一方、ICE(移民・税関捜査局)のホーマン氏は「移民法の執行を妨害する者は、取り締まりの対象になる」と警告しています。
次期民主党の大統領候補の一人と目されているニューサム知事は、メディアに目を引く発言を繰り返す姿勢が見られます。
ですが、現地住民の中には、一刻も早い治安回復を望む声が多く、警察の力が不十分であるならば、州兵や軍隊の投入を歓迎する意見も少なくありません。
不法移民を保護するあまり、合法移民や米国一般市民の安全を脅かすことがあっては本末転倒です。
これは例えば外国人学生に授業料や生活費を補助し、日本人苦学生への支援をしない日本政府と同じ考え方ですね。
【豆知識】
日本の人口推移
日本の人口は、近代化とともに急激な増加を遂げました。以下は主要な時期における人口の推移です。
江戸時代初期:約1,200万人
江戸時代末期から明治初期:約3,340万人
明治時代の末:約5,000万人
昭和初期:約7,000万人
終戦直後:約8,000万人
昭和42年:1億人突破
(出典:JICE www.jice.or.jp, 国土交通白書www.mlit.go.jp )