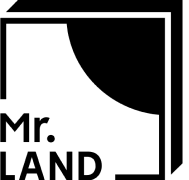【経済の動き】米国株絶好調
米国の株高が続いています。FRBの政策金利は高止まりしており、トランプ関税による先行きの不透明さが指摘されていますが、経済指標から見ると米国経済は好調に見えます。インフレ率や失業率はいずれも低く、雇用は底堅い状況が続いています。投資家は消費の減少や不動産市場の不調にはあまり関心を示していないようです。株高の理由の一つは、海外から米国への資金流入です。海外から米国市場への資金流入によって、ドル高も進んでいます。これは海外からの投資が、自国通貨を売って米ドルを買うことになるためです。
米国債利回り高止まり
米国債の利回りが高止まりしています。これは米国債が売れていないことを意味します。投資資金は国債ではなく、株式や金に向かっています。米国債は元本が保証されているため、インフレに弱いのです。そのため、インフレ懸念がある場合は利回りが上がります。逆に、インフレになると値上がりするのが株式相場や不動産価格です。
日本の景気はどうなる?
日米関税交渉は一応15%で落ち着きました。そのニュースを受けて、日本株は急騰しています。
また、日銀はこの状況を受けて、年内の利上げを示唆しています。利上げが実施されれば、市場は円高に動く可能性が高いでしょう。これは、上がり過ぎたドルを押し下げる方向に働きます。利上げは米国の意向を受けて行われる可能性もあります。ドル安は米国の輸出を容易にしますが、逆に円高は日本の輸出関連企業や世界に拠点を持つ大企業の利益を圧迫します。関税の上昇で輸出量が減少し、さらに円高で利益が下がれば、日本経済は後退するおそれがあります。景気後退を避けるには、日本国内の消費を刺激することが必要です。
やはり、消費税を廃止して国民の消費を増やせるかどうかが、今後の日本経済を左右するでしょう。
日米関税交渉は成功か?
日米関税交渉が妥結し、鉄鋼とアルミを除き、関税率は25%から15%へ引き下げられました。しかし、その内容は日本の大幅な譲歩によるもので、日本から米国への資金流出を招く可能性があります。これでは交渉成功とはとても言えません。
自動車関税は現行の2.5%から15%に引き上げられました。表面上は日本の国益を守ったように見えますが、全体的には日本の国益を損なう内容となっています。
以下、詳細を見ていきましょう。
- 日本が米国へ5,500億ドル(約80兆円)を投資する。利益配分は米国90%、日本10%。
- その80兆円はどこから捻出するのでしょうか?国民の税金でしょうか?
- コメと自動車の市場を開放し、コメの購入を75%増加。
- 農産物やその他の製品を80億ドル(1兆2,000億円)分購入。
- ボーイング社の航空機を100機購入。
- 米国防衛関連企業から防衛装備品の購入額を140億ドルから170億ドルへ引き上げ(日本円にして2兆5,000億円)。
今回の日本の関税交渉妥結には、交渉中の各国に向けた米国からのメッセージが含まれているのではないでしょうか。「米国市場への投資があれば関税率は下がる」というものです。米国市場で製品を売りたい国は、ある程度の妥協を覚悟せざるを得ないでしょう。対米輸出が黒字の国は交渉において米国が有利になります。
こうした背景を踏まえると、米国の関税交渉は米国内への投資と利益を増加させ、一時的なインフレや景気後退があったとしても、最終的には米国の一人勝ちにつながるでしょう。米国経済の見通しが明るいため、米国へ資金が流入していると考えられます。
【不動産・住宅ローン金利動向】 不動産販売低迷
不動産販売は新築・中古ともに不調です。この不調の理由は、物件価格とローン金利の高止まりにあります。物件価格が高いのは、コロナ禍における高インフレが原因です。さらに、インフレ対策としてFRBが政策金利を引き上げ続けたことや、トランプ関税による将来のインフレ懸念が米国債の利回りを押し上げていることも影響しています。米国債の利回りは長期金利の指標となり、この長期金利が住宅ローン金利の決定に反映されるためです。
その結果、不動産関連業界は低迷を続けています。これは米国経済にとって大きなマイナス要因です。もし銀行を含む不動産関連の金融業者が倒産し始めれば、連鎖的に倒産する企業が増える可能性があります。一度連鎖が始まれば、FRBによる利下げでは止められません。だからこそ、今のうちの利下げが必要なのです。
住宅ローン金利
ローン金利が下がるきっかけは、FRBによる継続的な利下げや、市場が「インフレはもう心配ない」と確信したときです。現在は、そのどちらも起こっていないため、当面は金利の高止まりが続くでしょう。好条件でも30年固定金利は6.5%前後です。
9月にFRBの利下げが予想されていますが、少なくともそれまでは大きな金利低下は期待できそうにありません。
FRBは政策金利を下げるべき
FRBは金利を下げるべきだと考えます。現在、雇用が底堅く先行きが不透明であることを理由に、FRBは金利を据え置いています。しかし、この金利高止まりは社会全体の資金調達コストを押し上げています。債券発行による直接金融も、銀行融資による間接金融も、いずれも金利が高止まりし、特に製造業では国際市場での価格競争力が低下しています。
さらに、コスト上昇はインフレ抑制どころか、むしろインフレを加速させかねません。中小企業や未上場企業の資金調達コストはより高くなり、事業継続が困難になる企業が増えています。小売業や飲食業などでも、閉鎖を余儀なくされるケースが目立ちます。
インフレ率が上昇しても、消費が増え企業収益が拡大し、賃金も上昇すれば問題はありません。しかし、現在はそうなっていません。
需要増加によって起こるインフレを「デマンドプル型インフレ」と呼びます。このタイプのインフレを抑えるには、供給を拡大することが必要です。供給量を増やしインフレを抑制しつつ、消費を喚起することが好景気の流れです。
こうした点を踏まえれば、FRBはできるだけ早期に金利を引き下げるべきでしょう。
【国際ニュース】ゼレンスキー大統領
最近、ゼレンスキー大統領に関する報道がめっきり減りました。国際会議でのニュースもほとんど聞かれません。実はウクライナ国内でも、ゼレンスキー大統領の人気は急速に低下しています。
キエフ、オデッサ、リヴィウ、ドニエプルなどでは、反ゼレンスキーの抗議集会が拡大しています。その背景には、ゼレンスキー大統領が国家汚職対策局と汚職対策専門検察庁の独立性を剥奪する法律の制定を推進していることがあります。この法律への反対は、大統領自身が汚職で立件されることを恐れているためではないかと指摘されています。
抗議デモの参加者たちは「ゼレンスキーは悪魔だ」「恥辱だ」「反逆だ」と叫び、キエフのクリチコ市長も「ゼレンスキー政権は戦争を口実に反汚職機関を解体し、ウクライナを権威主義に向かわせている」と非難しています。
ウクライナはもともと汚職の多さで知られる国です。世界各国からの支援金や武器弾薬が行方不明になっているとも言われています。
【豆知識】
米国で最も固定資産税が低い都市ベスト10
日本の人口は、近代化とともに急激な増加を遂げました。以下は主要な時期における人口の推移です。
- Birmingham, AL
- Menphis, TN
- Louisville, KY
- Phoenix, AZ
- Nashville, TN
- Las Vegas, NV
- Indianapolis, IN
- Oklahoma City, OK
- Charlotte, NC
- Tampa, FL
(出典:Lendingtree https://www.lendingtree.com)