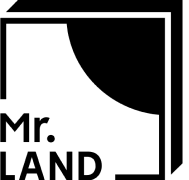【経済の動き】 FRBのパウエル議長が講演
8月22日、FRBのパウエル議長は、ワイオミング州ジャクソンホールで毎年恒例のシンポジウム講演を行いました。
市場が注目していたのは「9月に利下げがあるのか」という点でした。講演の中でパウエル議長が労働市場のリスクに言及したことから、利下げの可能性を示唆したと受け止められ、米国債は買われ、利回りが下落。ドル円は一時146円台後半まで上昇しました。
ただし、9月の利下げ幅が0.25%なのか0.5%なのか、または今後も連続して利下げが続くのかは依然として不透明です。今後発表されるPCE(個人消費支出)や雇用統計次第で変わる可能性があります。そのため25日(月)には米国債が売られ、利回りが上昇。ドル円も147.74円に戻しました。
不安定な米国労働市場
パウエル議長は講演で「労働市場は供給と需要の両面が鈍化し、奇妙な均衡状態にある」と述べました。
つまり、求人は減少している一方で、働く意思のない人も増加しており、労働環境は厳しいが失業率は大きく悪化していない、という状況を指摘したものです。
統計上は失業率が微増にとどまっているのは、「働く意思がない人」が増えているためです。移民の流出や退職者の増加も要因でしょう。物価高で生活費が上昇すれば、退職者が再び労働市場に戻り、結果として失業率が上昇する可能性があります。生活苦が広がれば犯罪率の上昇にもつながりかねません。
この点でパウエル議長は「奇妙な均衡」と表現したと考えられます。関税による物価高の対策としては、関税収入を活用した減税や低所得者への現金給付が有効でしょう。これはトランプ大統領が推進している政策と一致します。
しかしFRBの高金利政策は政府の政策と食い違いがあり、犯罪や生活不安といった社会課題に直接対応するものではありません。この点で財務省とFRBの間にずれが生じていると考えられます。
トランプ大統領が強く利下げを求めてきた背景には、FRBの独立性を脅かすというよりも「国民生活を真剣に考えている」姿勢があったのではないでしょうか。
金融危機がドル高を引き起こす
世界のどこかで金融危機が起これば、各国でドル需要が急増します。今もっとも懸念されているのは中国経済です。既にドル資産調達プレミアムは上昇しており、ドル需要の高まりが見られます。
中国経済の悪化が世界の債券市場に波及すれば、米国資産への大規模資金流入が起こるでしょう。実際に中国国債の利回りは大幅に下落しており、日本でも円キャリートレードを通じて米国債への資金流入が起きています。
また、工業需要を示す銅の価格はこの1か月で21%も急落しており、トランプ関税の影響による需要減退を反映しています。これらは「中国発の金融危機」の可能性を示唆しています。
トランプ関税もドル高要因
トランプ大統領の関税交渉の結果、米国への投資が増加しています。各国通貨がドルに替えられ米国に送金されるため、ドル高が進行します。
ドル高の影響は先進国よりも新興国に強く現れます。特に中国経済と結びつきの強い新興国では一層の悪化を招く可能性があります。短期的にはドル安でも、中長期的にはドル高へ向かうと予想されます。
【不動産・住宅ローン金利動向】 不動産価格が下がる理由
8月21日に発表された「米製造業PMIの上昇(需要拡大で3年ぶり高水準)」というニュースは、インフレ懸念を呼び、米国債利回りを押し上げました。
一方で新規失業保険申請件数は増加し、労働市場の減速も報じられましたが、市場の反応は限定的でした。景況感指数や失業統計の間に食い違いがあり、解釈が難しい状況です。
私の見方では、売上高が伸びているのは「仕入れコスト上昇を販売価格に転嫁した結果」であり、これはコストプッシュ型インフレといえます。さらに関税引き上げによって仕入れコストが上昇する懸念から、企業が先回りして仕入れを増やしている可能性もあります。
一方、不動産関連は既にスランプに入りつつあります。金利が高止まりすればさらに悪化するでしょう。たとえ金利が下がっても、物件価格が高止まりしているため購入者は限られ、取引件数は伸びにくい状況です。
結果として、不動産価格は下落圧力にさらされています。CPIの約40%を占める不動産価格が下がれば、インフレ率も低下し、消費にも影響します。中古不動産取引はGDPに反映されませんが、景気後退リスクは確実に高まっています。
不動産価格下落はローン金利低下につながる
不動産売買の低迷 → インフレ率低下 → 株価下落 → 米国債買い → 利回り低下 → 長期金利低下 → 住宅ローン金利低下、という流れが見込まれます。
中国からの資金流出と合わせて米国債需要が強まれば、ローン金利はさらに下がっていくでしょう。
【国際ニュース】中国恒大集団の隠し資産
かつて中国最大手だった不動産デベロッパー恒大集団は、8月25日に香港証券取引所から上場廃止となりました。負債総額は約49兆円。購入者は入居できず、ローンだけが残り、悲惨な状況に陥っています。
また、従業員給与や下請け業者への未払いは約30兆円に上ります。現実的には債権者が資金を回収する方法はなく、創業者一族の海外資産に頼るしかありませんが、既に保全措置が取られており困難な状況です。
不動産に資産を偏らせてきた中国経済は、不動産不況により深刻な打撃を受けています。庶民の生活は厳しく、富裕層は資産を海外に逃避させています。日本は円安と生活コストの低さ、安全性などから、移民の受け皿の一つとなりつつあります。
【米国不動産豆知識】 米国の引っ越し事情
- 米国人の生涯平均引っ越し回数:11回
- 引っ越しのピークシーズン:夏休み期間(5月末~9月初め)
- 今年、カリフォルニアからの引っ越し先が多かった州:テキサス、コロラド、テネシー
- 最も流出人数が多かった都市:ヒューストン、デンバー、ラスベガス
出典:The Sacramento Bee